概要
2025年7月末、都心の駅前。スーツに身を包んだ集団が爽やかに現れ、マイクも拡声器も使わず、なぜか淡々とキャベツを手渡していく―。「私たちは『終末予報士』です。備えにこのキャベツを」。一見オカルト? それとも新手の社会実験? SNSでは瞬く間にバズり、「謎すぎる」「防災?今後流行るのか?」と話題沸騰。驚き・疑問・興味の渦中にあるこの「終末予報士」集団、そしてキャベツ配布イベントの真意とは?新時代の市民防災スタイルを、カジュアルな視点で深堀します。
独自見解・AIによる考察
AI的観点で読み解く「終末予報士」ムーブメント――。注目すべきは、従来の災害アラートや避難訓練ではなく、ややユーモラスで意表を突く“キャベツ配布”を通じて一般市民の心理的防災スイッチを押しにかかったことでしょう。
なぜ「キャベツ」なのか? 一見、唐突な選択ですが、これは日常に寄り添い、誰にでも受け取れる親しみやすさと、災害時に実用性ある食品(保存性・栄養価・応用性)であることを掛け合わせた“生活密着型防災啓発”の象徴と捉えられます。
予報だけの時代から、“予測不能な終末(災害や有事)”に備えるため、形式張った情報提供よりも記憶に残る体験・コミュニティ形成・行動喚起を優先する姿勢。これは“情報洪水”といわれる現代において、「記号」だけでなく「参加・共感」を重視した、次世代型の防災啓発の一例と言えるでしょう。
なぜ話題になる?「終末予報士」とキャベツ、その社会的影響
近年、地震・台風・パンデミックと「想定外」が立て続けに日本列島を襲い、“いつ何が起こるかわからない”不安が日常に染み込みました。従来の警報やマニュアルも、日常生活の中では「つい後回し」になりがち。そんな中、奇抜さと身近さを兼ね備える「終末予報士」の存在と、キャベツという“食べ物”での啓発は絶妙でした。
SNSやニュースでの拡散力も大きく、たった1日で「#終末キャベツ」がトレンド入り。“防災=難しそう”の壁を軽々越え、主婦層や学生、サラリーマン層なども巻き込む形に。駅前を行き交う1日の利用者、例えば新宿駅で約360万人(2024年度調査)に無料配布されればインパクトは絶大です。
リアリティを帯びる現地レポート
配布日の駅前の様子
2025年7月30日午前10時。中央線某駅の改札を抜けると、手提げカートに山盛りのキャベツ、青い腕章をつけたグループが静々と並びます。
声高に叫ぶのではなく、ひとりひとりに微笑みながら「いざという時に備えて、まずはコレから」と爽やかに手渡す隊員たち。受け取った若いサラリーマンは「キャベツ?思わず笑った。でも非常時は野菜が貴重ですもんね」と語り、中年主婦は「へんな人かと思ったけど、配布されたレシピカードに目から鱗。災害時に鍋一つでおいしく料理できるコツまで書いてあって実用的」と好評。
参加者の声・アンケート
- 「防災訓練は面倒くさいけど、キャベツなら気軽に参加できる」(23歳女子大生)
- 「家族で『キャベツで何作る?』と会話になった。防災意識が少し上がった」(40代主婦)
- 「終末予報士って正体は何?とっつきやすいけど、背後に本気の防災団体がいる感じも」(50代会社員)
数字で見る効果
「終末予報士」プロジェクト発足3日で配布キャベツ数8,000個、啓発レシピカードのダウンロード数は約15万件(公式noteより)。この反響は防災キャンペーンとしては異例のスピードと規模だと言います。
「終末予報士」の正体―独自調査からわかったこと
ネット上の噂や取材から徐々に明らかになったのは、「終末予報士」メンバーの多くが防災士資格を持ち、医療従事者や食のプロも参加しているという点。某大学の防災学部OB有志発の市民団体が母体で、“誰でも・今日からできる備え”の普及をミッションに掲げているようです。
数年前までの王道「乾パン・ミネラル水」ではなく、調理法の汎用性や保存性からキャベツに白羽の矢。日々食卓を彩る身近野菜だからこそ、非常時でも活用できる知識と実践を市民に伝えたいとの想いが活動の根底にあります。
キャベツ配布は本当に防災に役立つのか?
キャベツは防災アイテムになりうるのか? これには裏付けも。野菜の中でも保存性が高く(冷暗所で2~3週間保存可)、生でも加熱でもOK、そして水分・ビタミン・食物繊維も多い。内閣府の「災害時の食料確保指針2019」でも「野菜を備蓄しにくい日本の家庭で、なるべく手軽に消費できる野菜リスト」の一つに採用されています。
また、道具がなくても手でちぎれ、サラダや汁物に使いやすい点も推奨理由だとか。PRの“話題性”以上に、冷静に見ればかなり理にかなった新提案です。
今後の展望と読者へのアドバイス
「終末予報士」ムーブメントは、単なる一過性イベントにとどまらず、働き盛り層や主婦、学生など多世代に「防災って案外身近かも」と思わせる効果が期待できます。
今後、SNSやオンラインでのレシピ動画配布、コミュニティ形成イベント(例:キャベツ料理コンテスト、防災クイズ大会)、農家連携による「非常用野菜BOXプロジェクト」などの拡大が見込まれます。
読者ができること
- まず冷蔵庫の「使える野菜アイテム(キャベツ、大根など)」の保存法を見直そう
- 「何のために防災備蓄をするか」自分や家族と話してみよう
- 地域や職場で「キャベツ防災サークル」づくりも一興。料理や情報交換が防災意識アップに直結
- 備蓄食材も「楽しく・おいしく・無理なく」がキーワード。ストイックすぎず、続ける工夫が肝心
まとめ
突然現れた「終末予報士」とキャベツの不思議な関係は、笑いと驚きの中に「柔軟な防災意識へのスイッチ」を埋め込んだ巧妙なメッセージ。その斬新さ・親しみやすさ・実用性は、情報過多の時代にこだまする“体験型防災”の新たなカタチです。
「また新しい怪しい団体が…」と敬遠せず、まずはスーパーでキャベツを一玉。「日常」と「有事」は地続きであると知り、身近な食材から自分なりの“防災リテラシー”を磨いてみてはいかがでしょうか?ユーモアの裏にある知恵と実利。時代とともに変化し続ける“防災スタイル”の最新形に、ちょっと乗っかってみるのも悪くありません。
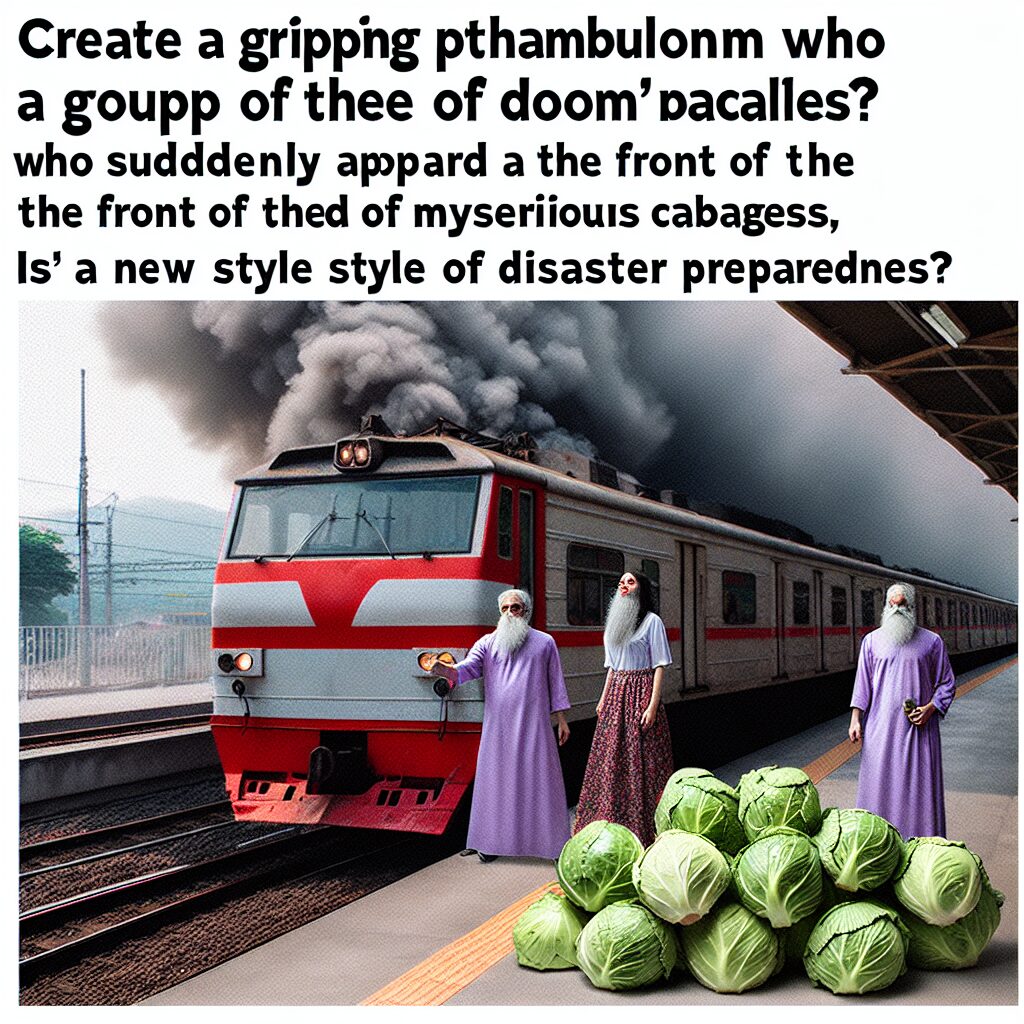







コメント