呼称一つが家庭を揺らす
「じいじって呼ばないで」と祖父が言った日
「孫に“じいじ”って呼ばせないでくれないか」
ある40代の女性は、出産後、父親からそう頼まれて戸惑ったという。
「えっ、普通の呼び方じゃないの?」と聞くと、返ってきたのはこうだった。
「“じいじ”って、なんか他人事みたいで嫌なんだ。呼ばれてもピンとこないし、少しバカにされてる気がする」
確かに、SNSでも「“じいじ”って響きがどうも無理」「“ばあば”って甘ったるくて引く」といった声は少なくない。
家族の中でごく自然に使われてきたはずの呼び名が、いまや世代間でモヤモヤの火種になっている。
なぜ「じいじ・ばあば」が増えたのか?
この呼び方は、1980年代以降、テレビや児童向け絵本、育児メディアを通じて広まり定着したとされる。
「おじいちゃん・おばあちゃん」よりも発音が簡単で、言葉を覚え始めた幼児にも言いやすいため、育児現場では“親しみやすく便利”な呼び名として重宝されてきた。
保育園や児童館では、保育士が「今日はじいじとばあばに会いに行くのかな?」と自然に声をかけ、
その影響で子どもが「うちのじいじ」と話し始めることも多い。
だが、ここで忘れてはならないのが、その呼び名をどう受け止めるかは“呼ばれる側”の感覚に依存するという点だ。
呼び名が生む“違和感”の正体
名古屋市の63歳男性は、初孫に会った日、こう思ったという。
「“じいじ!”って呼ばれても、“あれ?自分のこと?”って少し間が空くんです。
子どもっぽい響きに感じてしまって、“もっと普通に名前で呼んでくれていいのに”と思った」
東京在住の30代女性もこう語る。
「“ばあば”って、なんだか“キャラ化”されてるみたいで嫌。
テレビの中の登場人物のような、作られた立場にされる感覚がある」
呼び名には、その人の年齢観、家庭観、立場への自己認識がにじむ。
つまり、じいじ・ばあばという響きに「かわいらしい年寄り像」を感じる人と、
「幼児語に扱われたような屈辱」を感じる人がいる、ということだ。
親世代の意向が“呼び名”を決める構造
では、子どもはどうして「じいじ・ばあば」と呼び始めるのか。
答えはシンプルで、**最初にそう教えるのは“親”**だからである。
「おじいちゃんに“ありがとう”って言ってごらん?」ではなく、
「じいじに“ありがとう”は?」と教えれば、子どもはそのまま学習する。
つまり、“子どもの呼び方”に見えて、実際は親の価値観が祖父母に投影されているケースが多い。
これに対し、祖父母側から「そう呼ばれるのはちょっと…」と申し出たとき、微妙な緊張が家庭内に生まれる。
親からすれば「めんどくさいな」、祖父母からすれば「勝手に決めないでほしい」という静かな心理の衝突だ。
多様化する呼び方と“家族の距離感”
近年では、「グランマ」「グランパ」「ネーネ」「ポポ」など、家庭独自のニックネームを設定する家庭も増えている。
また、あえて名前に“ちゃん”や“さん”をつけることで、「祖父母=固定された役割」から解放されたいと考える人も。
東京大学の社会言語学者・湯浅彩子准教授はこう語る。
「呼び方は、単なる音の問題ではありません。
家族内で誰が誰にどう接しているか、どう見られたいかという、関係性の微調整が凝縮された記号です」
つまり、家族の呼び名にはそのまま人間関係の温度・立場・世代間の調整が詰め込まれている。
じいじ・ばあばをめぐる違和感とは、単に言葉の問題ではなく、「この家族の中での自分のポジションはどうあるべきか」という問いでもある。
まとめ:呼び方に“正解”はない。でも、気遣いはできる
「じいじ」「ばあば」という呼び方が悪いわけではない。
それで心地よいと感じる人もいれば、そうでない人もいる。
重要なのは、呼ばれる本人がどう思うかに耳を傾けることである。
子どもに呼び名を教えるとき、少し立ち止まってこう考えてみてはどうだろうか。
「この呼び方は、誰のためのものか?」「呼ばれる本人にとって、心地いいものだろうか?」
呼び名ひとつで家庭が揺れる。
でもその分、呼び名ひとつで、家庭の距離がそっと縮まることもあるかもしれない。







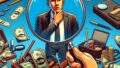
コメント