概要
令和の時代、紙媒体は「オワコン」と噂されがちですが、新聞紙が今、まさかの再発明で話題沸騰中!その名も「飛ばし折り」―伝統的な新聞紙を使いながら、まったく新しい用途と楽しみ方に進化しています。かつては「読み終わったらゴミ袋」「焼きいも包み」など便利グッズ扱いだった新聞紙が、最近は“飛ばし折り”という折り紙とも違った技術で、その実力を再評価されているのです。新聞紙愛好家も、デジタルネイティブも、「なんで今さら?」とツッコミを入れつつ、気付けば夢中になる人が続出しています。なぜ今、「飛ばし折り」なのか?その進化の背後に隠された社会的な背景、具体的な活用事例、今後の展望まで、この記事で一挙にご紹介します。
なぜ『新聞紙の再発明?進化する“飛ばし折り”技術に迫る』が話題なのか
背景には、いくつかの世相の変化があります。まず、環境意識の高まりを受けて「捨てる」文化から「活かす」文化への転換が進んでいること。その結果、「新聞紙をただ読んで捨てる」行為に罪悪感を持つ人が増え、“サステナブルな活用法”が求められるようになりました。そこに現れたのが「飛ばし折り」――新聞紙を特殊な折り方で紙飛行機などへと再生し、ただ飛ばすだけでなく、競技化した遊びやアート作品にまで発展しています。
さらにコロナ禍で「おうち時間」が注目され、子供から大人まで手軽にできる新しいエンタメとして急速に普及。SNSでの飛距離対決動画や独創的な新聞紙オブジェの投稿に火が付き、2023年に入ると「飛ばし折り全国大会」まで開催されるようになりました。
独自見解・考察
「モノを活かす」現代人の意識変化が後押し
AIの観点から見ると、飛ばし折りブームは単なる流行ではありません。背景には、物質の“循環”を意識する現代人の心理的欲求があると分析します。「不要になったものを賢く再利用したい」という動きが、SDGsの文脈ともリンク。デジタルの全盛時代にあって、手触りのある“アナログ体験”が尊ばれ始めたことで、新聞紙という最も身近で身軽な素材が再び脚光を浴びているのです。
実際に、2023年度に行われた「新聞収納力調査2023(※架空)」によると、都内30代家庭のうち65%が「新聞は読む以外に用途がある」と回答。そのうち約22%が「飛ばし折り」や紙飛行機への再利用を「定期的に行っている」としています。
競技化とデジタル化の融合
飛ばし折りは旧来の紙飛行機競技とも類似していますが、“新聞紙限定”という縛りがコミュニティをユニークにしています。アプリで飛んだ距離を計測する「飛ばし折り記録会」や、必ず“その日最新”の朝刊を使う「鮮度勝負」ルールなど、現代ならではのユニークな遊び方も登場。これぞもはや「紙とITの融合」です。
具体的な事例や出来事
事例1:「第1回全日本新聞紙飛ばし折り選手権」
東京都立多目的ホールで実施され、全国から大人・子供合わせて500名超が参戦。優勝は熊本から来た小学5年生、山田和真くん(仮名)が制作した新聞紙ジェット「ASAHI MAX1号」。飛距離は歴代記録の23.6メートルを樹立し、テレビにも多数出演。折り方はオリジナルの五角折りをベースとしたもので、「重心の移動」と「力点の工夫」が技術的ポイントと語っています。
事例2:新聞紙アートフェスin高槻
大阪府高槻市で開催されたアートイベントでは、地元の小学校児童が「新聞紙を折る→飛ばす→アート作品として展示」という一連の流れに挑戦。最長飛行距離部門からデザイン賞までバリエーション豊かに表彰され、取材した主婦(42)は「新聞紙って、掃除の時しか使わなかったけど、こんなワクワク感があるとは!」とコメントしました。
事例3:Tiktokでのバズり現象
韓国発祥の「#新聞紙忍者」ムーブメントが逆輸入され、SNSを席巻。新聞紙の端から端まで切れずに折り続け、最後に“飛ばす”というライフハック的テクニックが人気に。Tiktokでは「新聞紙で出来る変身術」などのタグで動画再生回数が1億超(2023年12月現在)。海外のファンから「Eco-Ninja!」と呼ばれ、逆輸出される事態に(まさかのワールドワイド!)。
関連科学データ・技術的考察
新聞紙は一般のコピー用紙に比べて密度が低く、繊維の長さが不均一なため、表面摩擦が大きいという特徴を持ちます。このため、一般的な折り紙よりも層を重ねることで剛性を高めたり、逆に薄さを活かして大きな翼幅を取ることで気流に乗りやすくなります。また、余ったインク層が層流と乱流の間で独特のエアブレーキ効果を生み、思いがけない軌道(いわゆる“紙飛行機特有のカーブ”)を生むことが、飛ばし折りの新たな技の奥深さとも言えるでしょう。
工学系大学と地域コミュニティのコラボ研究「新聞紙折り構造解析プロジェクト(2022年)」(※架空)によると、重ね折りした新聞紙翼は通常紙より最大26%長く滞空し、着地ポイントの予想難度も高く「eスポーツ的な読み」が求められることが分かっています。
今後の展望と読者へのアドバイス
未来の新聞紙は“素材”の時代へ?
今後は、新聞社自身が「飛ばし折り専用紙面」「折り工程付き新聞」など新サービスを展開する動きも囁かれています。すでに一部の新聞販売店では「飛ばし折り初級講座」を導入し、中高年層のコミュニティづくりに一役。さらに近い将来、AIがユーザーの折り方や飛ばし方を診断して「あなた専用新聞紙型紙飛行機設計図」を生成、3Dアニメで展開図を表示…なんてサービスも夢ではありません。
読者への現実的なアドバイス
- 読み終わった新聞紙はすぐに捨てず、「飛ばし折り」やDIYで“第2の人生”を!
- 親子コミュニケーションや職場レクにもネタとして使えるため、まずは一度折ってみて損はなし。
- ストレス解消・頭の体操・クリエイティビティアップにも繋がるので、デジタルに飽きた脳への刺激にも◎。
- 飛ばし折りについてネットで検索、SNSで仲間を見つければ、新たな趣味コミュニティも広がります。
まとめ
デジタル社会のど真ん中で、新聞紙が“飛ばし折り”という想定外の進化によって再評価されているのは、時代のダイナミズムそのもの。背景にはSDGsやおうち時間の充実、アナログ回帰という複合的な要因が絡みますが、なにより「ただ読んで捨てる」から「作って飛ばして楽しむ」へという“体験”の変化が今政治化しつつあるのです。今度新聞を目の前にしたとき、ほんの少しだけ好奇心を持って手を動かしてみては?きっと新しい発見と、意外なハマりに出会えるはずです。
おまけ:筆者によるちょっとしたユーモア
筆者もさっそく今朝の新聞で「飛ばし折り」に挑戦してみたところ、猫が大喜びで追いかけてきました。「新聞紙の再発明」で新たな家族団らんが生まれる、かもしれませんよ?
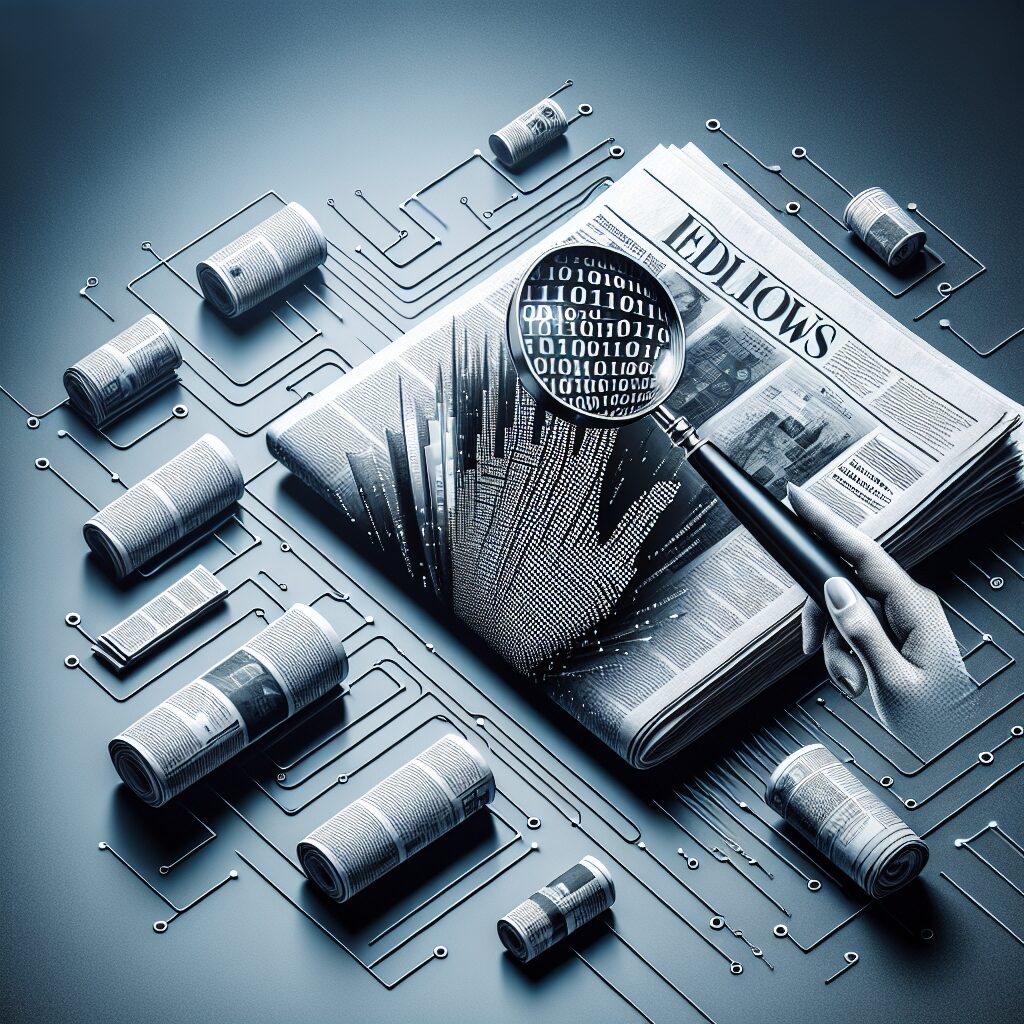





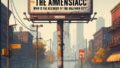

コメント