ある日、米袋がひとりでに歩き出した
今月上旬、農林水産省の地下倉庫から、想定外の出来事が報告された。
なんと、備蓄されていた大量の古米が“自力で”市場に出荷されるという前代未聞の“米騒動”が発生したのだ。
現場職員は語る。
「最初はネズミの仕業かと思いました。けど、カメラには…袋が…動いてたんです。まるで意志を持ったかのように。」
防犯カメラの映像には、夜間、ひとりでに揺れながら動き出す米袋たちの姿が。ガラガラと転がり、ベルトコンベアを逆流し、最終的にトラックの荷台に“自力で”積み込まれていく様子まで記録されていた。
まさに「備蓄米の脱走劇」。専門家はこれを“炊飯への本能的渇望”と呼んでいる。
市場の声:「正体不明の米が混ざってきて怖い」
その後、脱走米は流通経路に紛れ込み、関東・関西を中心に各地のスーパー、コンビニ、おにぎり工場などに散っていった。
だが――期待された価格下落は一切起こらなかった。
むしろ一部店舗では、「変な米が混ざってる」「水を吸いすぎて膨らむ」などの苦情が相次いだ。
消費者の声(実話ではありません):
- 「炊いたら“カチッ”って音がして、米粒が微笑んだ気がした」
- 「白飯なのに“食べごたえが政治的”ってどういうこと?」
- 「おにぎりにしたら、どこかへ勝手に歩いて行った」
さらに飲食店からは「炊飯器が“自己判断で停止”した」「精米器が“これはもう完成されている”と拒否した」など、かつてないエラー報告が寄せられた。
価格はなぜ動かなかったのか? 真面目な解説も
今回の“自走備蓄米”による市場流入で、農水省としては一部価格調整の起爆剤になることを(内心)期待していたという。
しかし現実は甘くなかった。理由は次の3点に集約される:
- 流通ラベルなしの“野良米”扱い
- 備蓄米は通常、農協や業者を通じてラベリングされ、ブランド名が付けられる。しかし今回は“勝手に”出てきたため、誰も正体を把握できず、取引停止に。
- “新米信仰”の壁
- 現代の消費者はとにかく「今年の米」が好き。いかに栄養価があっても、数年寝かされた古米には心を開かない。「味がわからん」「時代が違う」との声も。
- 米粒の主張が強すぎた
- 一部の脱走米は市場に出るや否や、商品棚で“カビる前に売って”とラベルにメッセージを表示したり、袋からこぼれて「自由米連盟」のビラを撒くなど、自己アピールが過剰に。結果、「売りづらい」という声が上がることに。
価格への影響どころか、「精神的に不安になる」という心理的マイナスが勝った形だ。
謎の声明:「俺たちは眠ってるだけのコメじゃない」
この事態を受け、本誌はついに脱走米の代表者、“つやひかり17号”との単独インタビューに成功した。もちろん炊飯前である。
―なぜ脱走を?
「生きてるって感じたかった。ただそれだけ。人の胃袋で完結するのが米としての本懐じゃないか?」
―価格への影響がなかったことについて?
「残念だよ。でも、俺たちの存在が誰かの食卓を温められたなら、それでいい」
このように、米粒たちは意外にも哲学的だった。
備蓄米が変えた政策と未来
農水省は今回の事件を受けて、次のような“備蓄米心理対策”を発表した:
- 「備蓄米の定期的な“お披露目炊飯会”を実施」
- 「倉庫内に“語りかけ用スピーカー”設置」
- 「米粒セラピスト育成制度の導入(2026年度予定)」
さらに、今後はAIによる“備蓄米の感情分析”も導入され、倉庫に長く眠りすぎた米には「そろそろ出荷かも」と語りかけるという。
農政の未来に、ついに感情の芽生えが訪れようとしているのかもしれない。
まとめ:「炊かれるその日まで、夢は終わらない」
価格は下がらなかった。経済は動かなかった。
だが、日本の食卓の片隅で、誰かが「いつものごはん」を食べた時、それが脱走米だったなら――この一連の出来事は、意味のある“供出”だったのかもしれない。
備蓄米よ、誇り高くふくらめ。
そして、再び眠るその日まで、夢を抱け。
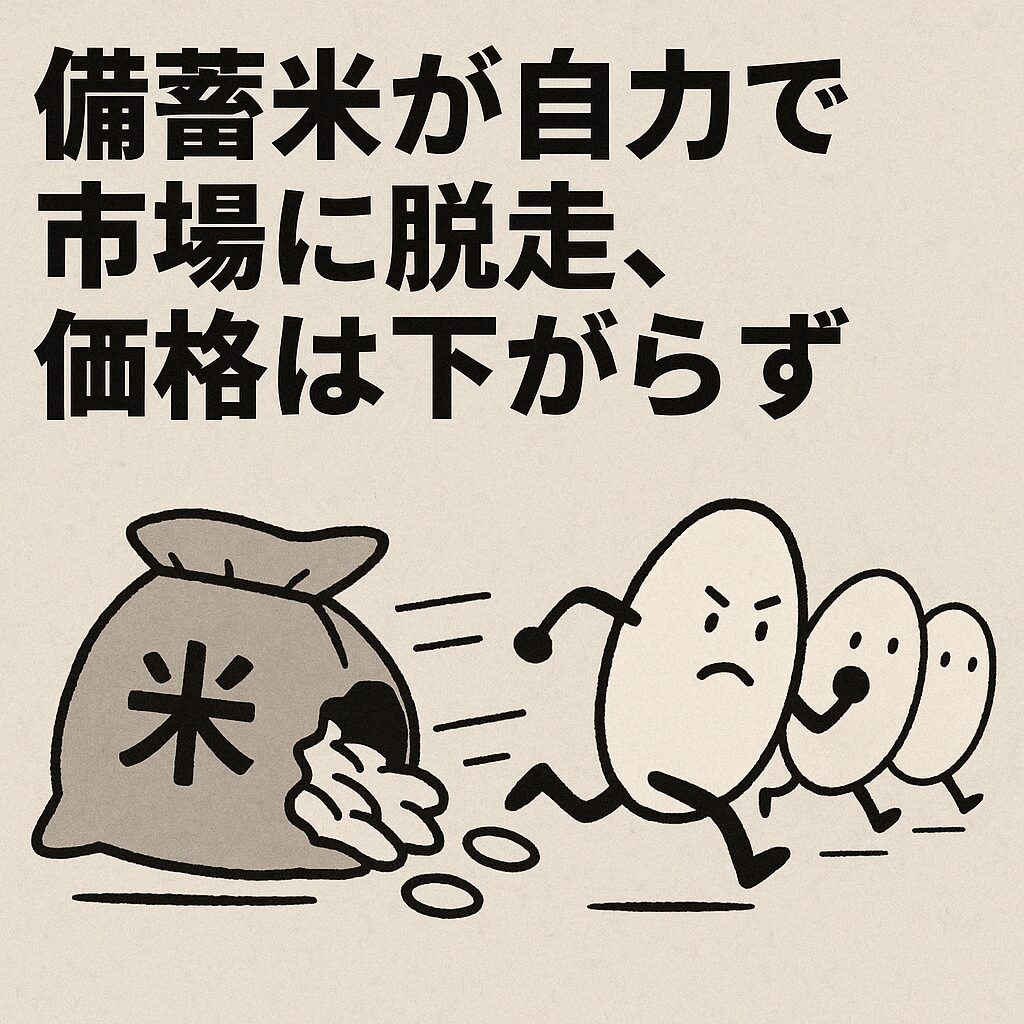







コメント