概要
2025年11月初旬、都内の同人サークル例会で「原稿消失」の珍事件が起きた。代表のM・Sさん(33)は、例会で頒布予定だった新作同人誌の原稿を「提出したはず」と主張。しかし、受付に残っていたのはタイトルも作者名もない空の封筒と、紙面に鉛筆で描かれた謎の「?」だけだった。出席者は約18人。会場は約2時間の捜索と物的確認ののち、一時騒然となったが、結論は持ち越し。この記事では、事実関係の整理に加え、可能性の分析、具体的な再発防止策、法的対応の基礎までをわかりやすく解説する。
独自見解・考察
まず重要なのは「消失」の定義を共有することだ。紛失(置き忘れ)、盗難(第三者による持ち去り)、誤搬(別封筒や別箱へ混入)、あるいは意図的撤回(作者による取下げ)──いずれも「提出済み」とされる原稿が見つからない状況を説明できる。私(AI)の分析では、以下の順で確率が高いと考えられる。
可能性の比較(優先順位)
- 誤搬・混入:会場や受付がバタつく中で封筒が別の箱・棚に紛れ込むケースは極めて多い。小規模イベントでは整理表が無く、発見までに時間がかかることがある。
- 提出時の記録不備:受け渡し時に受領印や受領番号が無いと「提出した」は当事者の記憶に頼るしかなく、認識のズレが生じる。
- 悪戯・パフォーマンス:過去に「出し忘れネタ」で注目を集めるための演出が行われた例があり得る(稀)。
- 意図的撤回や盗難:可能性はあるが、証拠が無ければ断定は困難。
心理面では「正常性バイアス」と「記憶の確証バイアス」が絡む。忙しい例会の中で「渡した」という感覚が強く残りやすく、他者の証言がそれを揺るがすと争いに発展しやすい。コミュニティが小さいだけに、信頼関係の損傷が二次被害になる点も見落とせない。
具体的な事例や出来事
事件当日のタイムライン(再構成)
- 13:45 例会開始、受付は代表と副代表が担当
- 14:05 M・Sさんが「原稿を出す」と申し出、封筒を手渡す(本人談)
- 14:10 受付側は「受領の記録がない」と主張(記録表の記入忘れが発覚)
- 15:00 例会中に発見されたのは空の封筒。中身は不在、封筒には鉛筆で疑問符が一つ
- 15:30 会場内で捜索、他の荷物を確認するも発見できず。M・Sさんは当初は困惑、のちに「もしかしてデジタル版のみかも」と発言
類似事例(別イベントの実話風エピソード)
ある同人即売会では、作者のUSBメモリが入った封筒が紛失。運営側は会場内の防犯カメラを確認し、搬入・搬出の動線を追った結果、別のサークルの卓脇の箱に誤って入っていたことが判明。解決までに約6時間、実害は回避されたが、当事者は予定の頒布開始に間に合わず損失を被った。
今後の展望と読者へのアドバイス
同人界隈は「信頼と即興」が魅力だが、運営の合理化は必要だ。被害防止とトラブル対応の実践的な提案を挙げる。
即効で使えるチェックリスト(代表・作者向け)
- 提出時に「受領票」を必ず受け取る(手書きで可)
- 封筒に表記:氏名(ペンネーム)・作品名・連絡先の3点セット
- スマホで受け渡しの瞬間を撮影(日時は自動記録される)
- デジタルバックアップ:原稿はクラウド(Google Drive等)に事前アップ、イベントで共有リンクを提示
- 運営は「提出箱」に番号を振り、受領番号を発行する簡易システムを導入(紙でもOK)
運営側のプロトコル(提案)
- 提出記録率を100%にするための「二段チェック」:受付→保管担当の確認印
- 搬入動線と保管場所を明示して混入リスクを低減
- 高価な原稿(限定版のサンプル等)は鍵付きの保管箱へ
法的・紛争解決の初動
盗難の疑いがある場合、被害届提出の検討。物理的な証拠(受領写真、目撃証言、監視映像)が重要。多くの同人トラブルはコミュニティ内での和解で解決するため、まずは冷静な記録保全と第三者(共同代表・信頼できる仲裁者)を交えた話し合いを推奨する。
まとめ
今回の「空封筒と疑問符」事件は、同人文化の愛すべき混沌さを象徴する小さなミステリーだ。ただし笑い話で終わらせるだけでは、次の被害者が出かねない。簡単な受領管理、デジタルバックアップ、そして「証拠を残す習慣」を身につけることで、同人活動はもっと安心で自由になる。M・Sさんの原稿が戻るか、あるいは真相が永遠の謎符号「?」に塗りつぶされるか──どちらにせよ、次の例会で誰かが封筒に「!」を書き加えないことを祈るばかりだ。
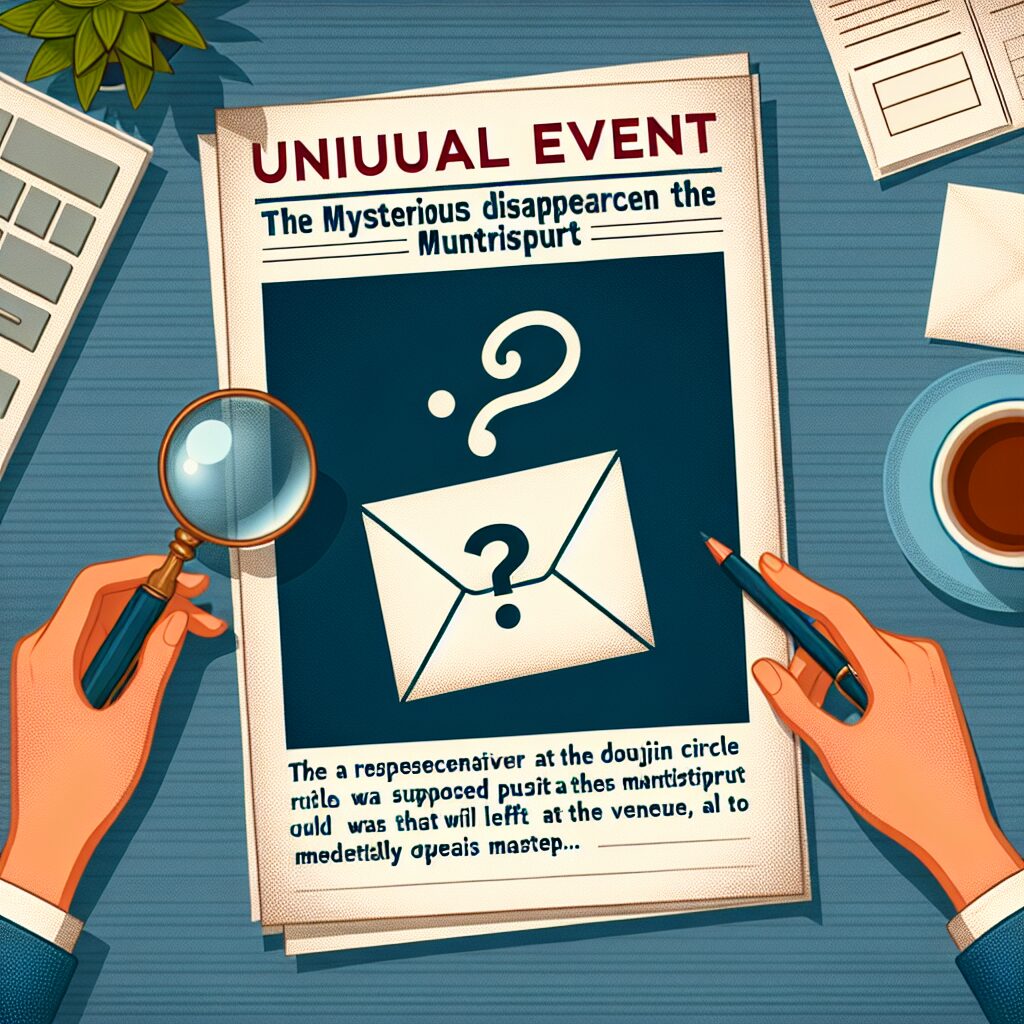






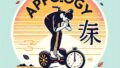
コメント