“無難力”が高すぎると、無に還る
「嫌われないために当たり障りなく話していたら、何も覚えられてなかった」
「会議で“誰にも反対されない発言”をしていたら、議事録に名前すら載らなかった」
――これは、令和社会における“無難コミュニケーション症候群”の代表的な症状である。
今やビジネスでもプライベートでも、「角が立たない」「空気を読んだ」発言が推奨される風潮だが、
あまりに“波風を立てなさすぎる”と、ついには**存在自体が“穏やかにフェードアウト”**していく。
SNSではこの現象を揶揄して、こんな言葉が広がっている。
「私の意見はありませんが、みなさんの意見を尊重します教の信者」
“空気が読める”と“空気になる”の紙一重
ビジネス研修などで推奨される「肯定ファースト」「柔らかい提案」「共感のあとに本題」は、一見すると人間関係の潤滑油に見える。
しかし、過剰な“無害化”が進むと、何も伝わらない・何も残らない・何も覚えられないという“三重の透明化現象”が起こる。
マーケティング会社のリサーチによると、「職場で“印象に残っている発言”が多い社員」の特徴として、
“少し主張が強い”“言葉にエッジがある”“時々本音っぽい”といった項目が上位にランクイン。
逆に「気遣い上手」「いつも相づちが丁寧」と答えられた社員は、“印象が薄い”との評価になりがちだったという。
本音を言わない社会は、“表面積”だけ増える
ある若手会社員(27)はこう語る。
「前の職場で“意見ある人は言って”と言われたので、『~は改善できるかも』と控えめに言ったら、翌週から“否定的な人”って噂されてました。
それ以来、“そうですね、たしかに”しか言ってません。でも誰からも話しかけられなくなってきました」
“波風立てない”を徹底した結果、人間関係の“起伏”までなくなっていく――これは令和の職場で多発している現象である。
しかもSNSでも現実でも、共感的すぎる発言はすぐに流れ、記憶に残らない。
つまり、「言わないことで傷つけずに済む」どころか、「何も残さないことで存在感すら失う」のが、今の“やさしすぎる会話術”の盲点なのだ。
AIの見解:「無難な発言は“内容”ではなく“存在”を薄める」
AI会話設計モデル「ToneMod v3.2」は、人間の対話ログを分析したうえでこう結論づけている。
「否定を避け、空気を読み、共感のみに偏った発言は、短期的には人間関係の衝突を回避するが、長期的には“存在の同一化”を招く。
つまり、“誰と話しても同じ印象”になりやすく、記憶されにくい」
これは「全員に好かれたい人ほど、誰からも覚えられない」現象のデータ的裏付けだ。
“まろやかすぎる発言”の量産がもたらす社会の鈍化
「なるほどですね」
「その可能性はありますね」
「色々考え方があると思います」
「一概には言えませんが」
――こうした“パンチのない共感語彙”は、あらゆる場所に蔓延している。
その結果、会議は長引き、意思決定は鈍化し、結論が出ないまま空気だけが充満する。
要するに、“誰も怒らない会話”は“誰も動かない会話”でもあるのだ。
会話における“個性”とは、角の鋭さではなく、適度なエッジと芯のある語調である。
それをすべて削り取った「完全に安全な発言」は、まるで塩気のないポテトチップスのように、存在意義を疑われ始めている。
本当に「角が立つ」のは、言葉ではなく“曖昧なまま放置すること”
東京の言語心理士・鈴木理沙氏は、こうした“無難すぎる会話”の流行を懸念する。
「多くの人は“言葉で相手を傷つけること”を恐れすぎています。
でも、実際に人を最もモヤモヤさせるのは、“言ってるようで何も言ってない態度”だったり、“本音を隠したまま逃げる姿勢”なんです」
“角が立つのを恐れて、話さない”のではなく、“角を丸くしてでも届かせようとする”工夫が、会話の本質だ。
まとめ:優しさと無難さは、似て非なるもの
「角が立たない」ことは確かに大切だ。
しかし、**“丸くなりすぎて透明になる”**のでは、会話は伝達ではなく“消音”になってしまう。
優しさとは、相手を思って言葉を選ぶこと。
無難さとは、自分を守って言葉を抜くこと。
この2つは、似ているようでまったく違う。
令和の会話術は、もう一度“聞かれる覚悟”を持つ時期に来ているのかもしれない。
あなたのその「はい、そうですね」の背後に、本当は何を言いたかったのか――
今日こそ、それを言ってみてもいい。
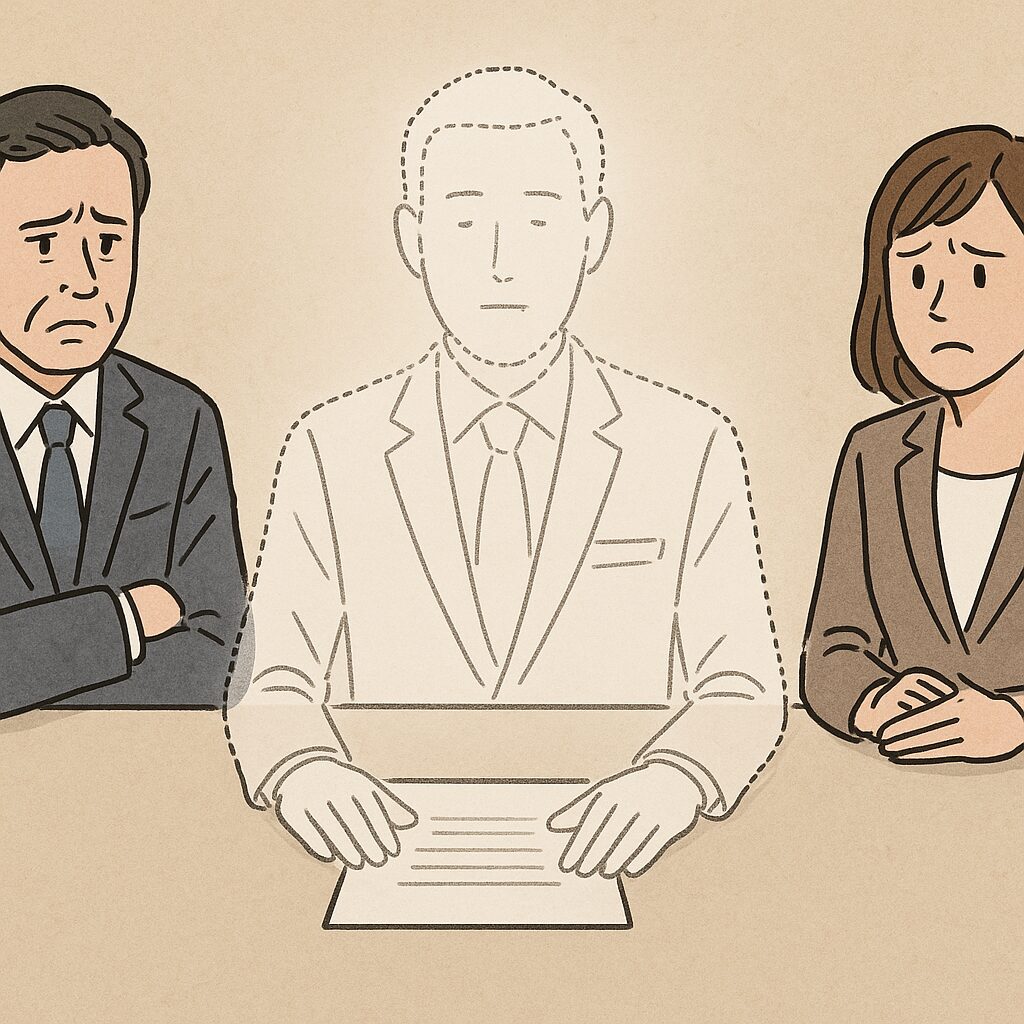







コメント
mfa57i