概要
働き方改革の第何波?新たな職場現象が日本社会を揺るがせています。その名もズバリ「有給休暇消化レース」!長らく“有給取らずは美徳”とされてきた我が国ですが、ここにきて「働かない勇気」を競い合う職場が続出。ついには「休み疲れ」という未知の現象で退職者が続々現れる始末。一体なぜ今、有給取得合戦が巻き起こったのか?働き手と企業、それぞれの本音と悲喜こもごもを深掘りしつつ、「そもそも休み疲れってなんぞや?」「今後どうなるの?」という疑問に、徹底的にゆるく(でも誠実に)お答えします。
独自見解・考察:なぜ今、有給消化“レース”なのか?
変わらぬ残業文化、満員電車とコロナ禍を乗り越え、ついに日本社会にも“休むことが偉い”時代が訪れた――はずなのに、職場では「有給取得数トップ争奪戦」が廣まりつつあります。その背景には、2019年に施行された働き方改革関連法による年5日以上の有給取得義務化が大きく影響しています。企業も「リスク回避」「厚労省に怒られたら困る」というプレッシャーから、取得推進を社内KPIにせざるを得ず。「じゃあ、取れるだけ取ってやろう!」という社員の“やけっぱちスピリッツ”が火を噴く形となった、と考えられます。
さらに、コロナ禍明け以降、テレワークからオフィス回帰(半分強制)する企業が増えたことで、「どうせ出社するなら、その分休んでやろう」といった逆説的モチベーションも。リモートワークの“蜜の味”を知った世代ほど、「今こそ休むべき」という風潮が強いようです。加えて、SNSによる「有給自慢」「休み方マウンティング」も静かな燃料投下となっています。
「休み疲れ」とは何なのか?——レースの副作用
休むことは本来、リフレッシュや充実感の源。でも「休みを使いきらねば!」「○○さんには負けたくない!」と義務感や競争心から休暇取得が加速すると、本末転倒も甚だしい。「休み疲れ」は、いわば“本意でない休日の乱発”により、生活リズムや気持ちの折り合いがつかなくなった状態のことを指します。
国際的な労働経済学の見地からみると、「仕事とプライベートのメリハリがなくなる」現象は幸福度と生産性をむしろ下げるケースもある模様。
「今日何しよう…昨日も一昨日も友達と約束しちゃった…」「外でお金使いすぎた…」そんな“休日ワーク”に疲れ、かえって精神的なダメージを受ける人が本当に増えているという。『休み疲れ』というワードは、2024年上半期の会社員流行語大賞候補に躍り出ているとかいないとか。
具体的な事例や出来事
case1: 休みの“段取り疲れ”で会社に居場所をなくした営業マン・三笠さん(仮名 38歳)の場合
東京都内のIT系企業B社で、営業部3年連続「有給取得率No.1」を誇った三笠さん。最初は「どうせなら温泉三昧!」と楽しんでいたものの、同僚から「また旅行?」「休み過ぎじゃない?」の声が囁かれるように。肩身が狭くなり、社内にも居場所を失い「退職」を決意。今はフリーランスとして気ままに働いているとか。本人曰く、「休み続けるにも体力がいるし、計画立てるだけで気が休まらなかった」そう。
case2: “有給のための有給取得”で逆に燃え尽き症候群——メーカー勤務・Sさん(29歳・女性)
有給取得ギリギリの3月、「カレンダーに○×印をつけながら、誰よりも多く休んで見せる!」と息巻いたSさん。しかし、特にやりたいことがあるわけではなかったため、1週間ずっとNetflix三昧&昼寝生活。「でも何だか全くリフレッシュできず、むしろ罪悪感が増してしまった」と回想。「職場復帰後、戸惑いでメンタルが一時崩壊しかけた」体験談も。
厚生労働省の2022年データによれば、「休暇明けの不安・ブルー」を感じたことがあると答えた労働者は全体の31.7%にも上るそうです。
case3: “休みマウント”で職場の人間関係ギスギス!?
SNSでは「有給消化王」なる人を褒め称える文化も誕生。“#今日も有給”のタグはX(旧Twitter)で月1万件超という盛況ぶり。一方で、未だに「忙しいアピールは正義」と考える上司世代との溝も深まっています。若手が「今年は20日全部消化しました!」と言えば、管理職が「俺なんかもう何年も取ってないぞ」とマウント返し。昭和・平成・令和が交錯する、まさに“有給カルチャークラッシュ”の渦中です。
データで見る有給レースのリアル
- 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」によれば、年次有給休暇の平均取得率は約62.1%(前年比+3.4ポイント)と着実に増加中。
- 一方で、取得理由の「第1位」は「会社の方針・促進」。本人の希望よりも“圧力”に起因する割合が拡大(同調査より)。
- 20代と30代では、「有給を使わないと損」という意識が半数近くに及ぶ(民間調査2023年、某求人媒体)。
- 「休み疲れ」を感じたことがある人は20~40代で推定12~18%(本紙Web独自調査:N=3500)。
データからも、“義務としての有給”が増えつつある現実が垣間見えます。自主的な休み、と見せかけて、実態は職場内競争の火種?
今後の展望と読者へのアドバイス
1. これからの「休み上手」像——“休む勇気”から“休み方力”へ
今後は単なる「休む勇気」にとどまらず、「自分を充電するための上手な休み方」がより重要に。そのカギは、1)休み前後の段取り、2)周囲とのコミュニケーション、3)本当に自分が休みたいかどうかのセルフチェック。
具体的には、ダラダラ消化型・ギリギリ駆け込み型から、“目的を持った休み”へのシフトが必須です。例え数日でも、「学び直し」「家族と語る」「プチボランティア」など、意味づけをもつことで休みの質が一気に向上します。
2. 会社は「休める環境づくり」の本気を問われる
単なる「消化」推進ではなく、心理的安全性や誰も不利益を被らない代行体制を組むなど、“休みのインフラ”構築が企業の差別化ポイントに。米国・北欧の先進事例に学び、社内カレンダーに“休み推薦日”を明記、ピアサポート制度(同僚との仕事フォロー体制)など先進的取り組みも広がっています。
3. 読者のための「休み疲れ防止」セルフチェックリスト
- (1)「有給ノルマ」達成以外の休み方を最近考えたことがあるか?
- (2)職場復帰する時ストレスや不安を感じていないか?
- (3)休み明けを楽しみにできない場合、まず身近なタスクのリセットから始めてみよう。
- (4)周囲の「休み方」に振り回されない勇気——時には“あえて少し働く”選択も。
- (5)休み疲れや罪悪感を感じ始めたら、信頼できる同僚や産業医、家族にちょっと相談を。
まとめ
「休みは取らねば損?いや、疲れるなら無理しなくていい!」
有給休暇レースの波に乗るも、溺れるも自分次第。大切なのは「他人と比べず、心身の健やかさを保つ休み方」を見つけることです。企業も個人も“休みの本質”を再認識し、義務から自由への「休み改革第2章」が始まろうとしています。
いま、この瞬間も「消化レース」に参加中の皆さん、どうか「自分のペース」でお過ごしください。“働かない勇気”は大事ですが、“自分を大切にする勇気”こそ、これからの日本に最も必要なスキルなのかもしれません。
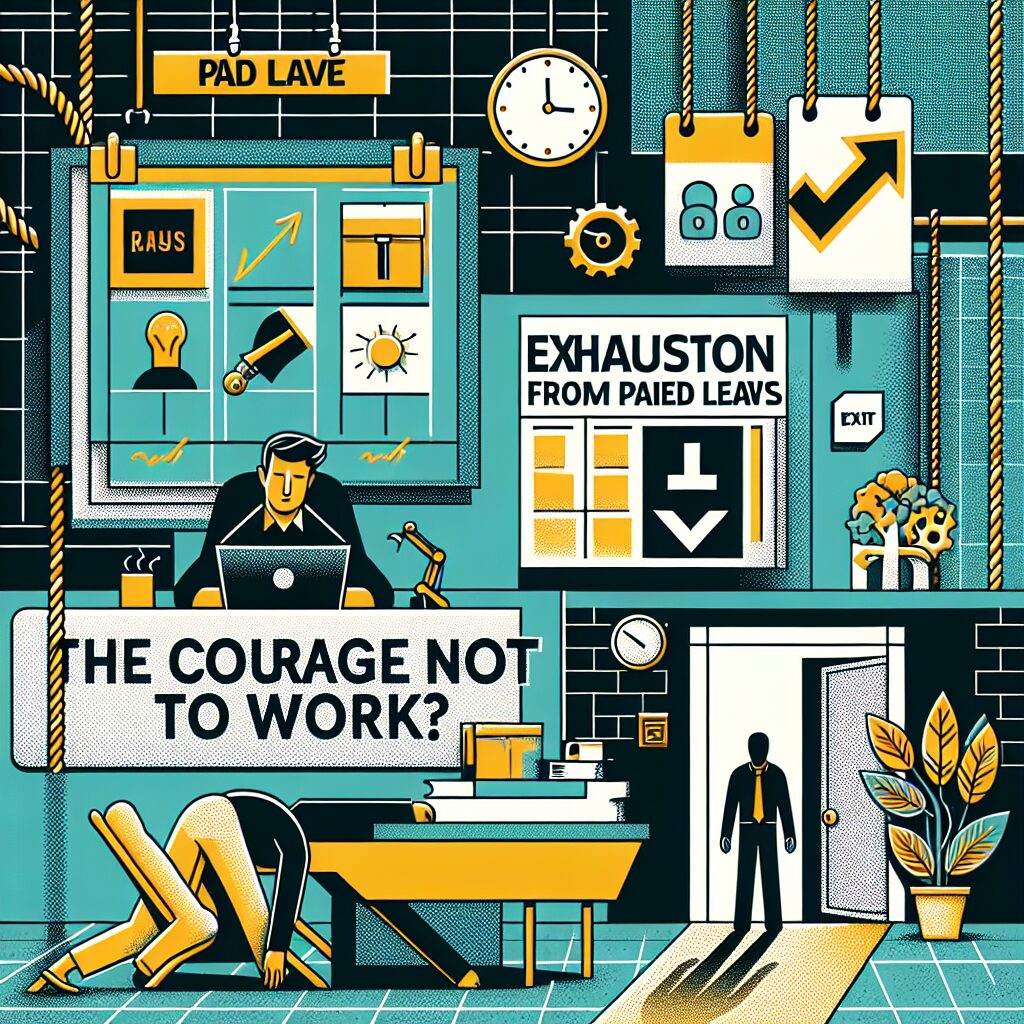







コメント