―コミュ障たちの「声なき拒絶」の行方
「人手不足」という名の招集令状
2025年春、政府が発表した新たな労働力確保策が全国に波紋を広げている。
対象は、主に就職氷河期世代(1970年代後半〜1980年代前半生まれ)。
かつて「自己責任」の名のもとに不遇をかこった世代に、
今、国は「建設・物流業界へ進軍せよ」という新たなミッションを与えた。
正式名称は「社会基盤支援就労促進プログラム」。
しかしSNS上ではすでに「招集令状」と揶揄されている。
対象世代に郵送された案内文はこう記されていた。
「あなたのキャリアと経験を、国の未来づくりに活かしてみませんか?」
「建設・物流分野では、あなたの力を必要としています!」
だが、受け取った当事者たちの心境は、
「未来づくりどころか、まず自分の未来が見えないんですが」
と、極めて冷えきっていた。
なぜ今、氷河期世代にターゲットが絞られたのか?
背景には、深刻な人手不足がある。
- 建設業界:団塊ジュニア世代の大量引退により、技能者数が急減。
- 物流業界:2024年問題(働き方改革による労働時間制限)でドライバー不足が深刻化。
若年層はそもそも業界に流れてこない。
外国人労働者の確保も、国際競争激化で難しい。
結果、「今まで放置してきた氷河期世代を動員せよ」という、
極めて場当たり的な方針が打ち出されたわけだ。
国土交通省関係者は本音を漏らす。
「正直、最後の砦として期待している。体力もまだギリギリあるし、教育コストも抑えられる。何より、もう『選り好みする余裕がない』」
コミュ障たちの静かな絶望
しかし、建設・物流業界が求めるものは単なる“労働力”ではない。
- チームワーク
- 現場判断力
- 短時間でのコミュニケーション能力
これらは、長年非正規や孤立無援の環境で「人とあまり話さずに済む職場」を選んできた氷河期世代にとって、最も不得意とするスキル群だった。
実際、試験的にプログラムに参加したAさん(46歳・元データ入力業務)はこう語る。
「建設現場で、朝礼のときに全員の前で『本日の作業確認』を求められたんですが……無理でした。声、出なかった。というか出そうとしたら咳き込みました」
同様に、物流センターでの仕分け作業を試みたBさん(48歳・元フリーター)は、
「周囲が怒号飛び交う中、伝票番号だけで指示が飛んでくるんです。会話じゃない、暗号でした」
と、適応できず数日で離脱したという。
SNSでは共感と諦めの声が続出
X(旧Twitter)では、
#氷河期召集令状 #無理ゲー転職
などのハッシュタグが急浮上。
投稿には、
- 「氷河期世代=自己責任と言われ続けた結果、自己防衛でコミュ力捨てたのに」
- 「建設業の人間関係をナメてる。昭和の体育会系そのもの」
- 「せめてチームに“コミュ障用ガイド”つけてくれ」
といった、
怒りと諦めのブレンドされた叫びが相次いでいる。
国の対応は「とにかく送り込む」
厚生労働省はこの声に対し、
「適性を見極めた上で配属先を決定する」
との建前を示しているが、実態は「現場に送り込みながら適応状況を見る」というほぼ実地任せのスタイルだ。
一部では、
「建設現場で喋れない氷河期世代を、さらに物流倉庫に回す“コミュ障リレー”」
なる現象も起きているという。
それでも希望はあるのか?
絶望一色に見えるが、わずかな希望もある。
- 一部物流企業では「無言仕分けゾーン」導入
(伝票スキャンだけで済む作業ラインを新設) - 建設業界でも「挨拶以外ほぼ無言」な現場も登場
(騒音が大きすぎて普通に会話できないため、結果的に静かな現場も) - 独自ルールを活かす新しい働き方提案
(例:ピクトグラム指示/LINEチャット指示)
つまり、「コミュ力ゼロでもなんとかなる現場」を探し当てれば、生き延びられる可能性はある。
問題は、その現場が限られていること、そして情報が表に出づらいことだ。
まとめ:静かなるサバイバルへ
氷河期世代に突きつけられた「建設・物流業への招集令状」。
それは、新たな希望の書状でも、救済の手紙でもない。
むしろ、
「自己責任で生き残れ」という、最後の冷たいメッセージ
なのかもしれない。
しかし、静かに、確実に生き残る者たちはいる。
「しゃべらない力」もまた、時には武器になる。
この飛び石だらけの社会を、
声なき者たちは、言葉を持たずに、歩き続けていく。
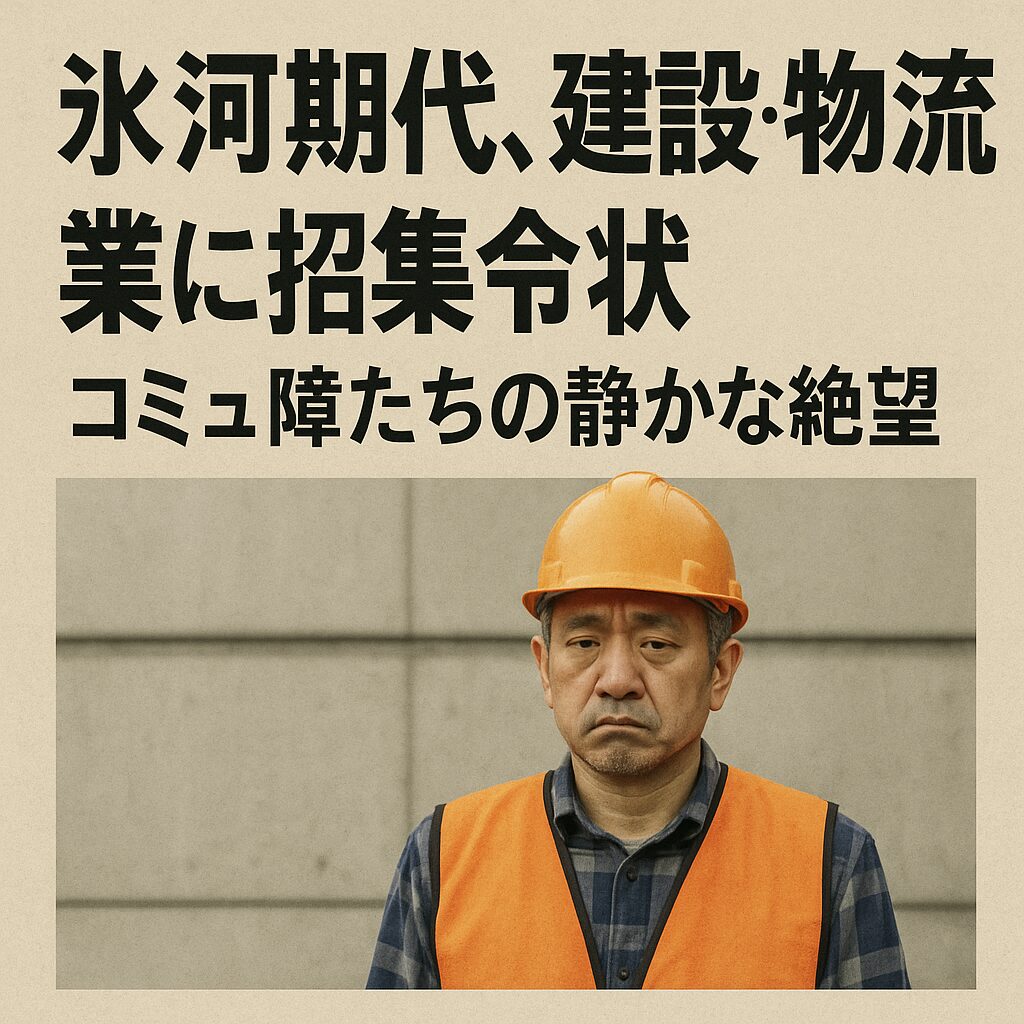







コメント