概要
東名高速道路、および中央自動車道でETCレーンの一部が突如閉鎖され、予期せぬ大混乱が発生している。普段は便利なキャッシュレス通過が売りの高速道路が、なんと「低速道路状態」に陥る始末。「高速道路改め、忍耐力選手権か」とSNS上でも話題騒然だ。ETC設備点検、改修工事が重なりドライバーには我慢のときを迎えているが、こうした珍騒動から現代交通システムのもろさや課題点を探ってみよう。
「ETCレーン一部閉鎖騒動」の背景は?
渋滞はなぜ発生したのか?
ETCシステムの一部施設が老朽化による設備更新や保守点検のため、複数の場所で同時に閉鎖が始まった。通常、各入口料金所に設置されたETCレーンはスムーズな通行を可能にするが、一部閉鎖によりETC搭載車両が一般レーンへと迂回したため通過時間が大幅に長引き、瞬く間に数十キロ規模の渋滞が発生。時間帯によってはまさに駐車場状態、「忍耐力選手権」の様相を呈する光景だった。
SNSでは怒りの絶叫(または諦めの笑い)で溢れる
TwitterやInstagramなどでは、「東名高速がまさかの低速道路化」「中央道で鍛える忍耐、これは新しい修行か」「もしや料金所でUターンして一般道のほうが速いのでは」という自虐的ツイートが多数見られた。ハッシュタグ♯忍耐力選手権、♯東名低速道路も一時トレンド入りするほどの盛り上がりだった。
ETCの現状と課題、私たちはどこで間違えた?
便利すぎるインフラはトラブルへの対応力に不安あり
今回の騒動は、日頃便利すぎてその脆弱性を忘れがちなETCという仕組みが、予想外のトラブルや設備更新のために容易に大規模渋滞を起こしうることを改めて私たちに突き付けた。ETCの使用率が約9割以上に達する現在、装置1本調整するだけでも影響は計り知れない。インフラの信頼性を維持するためには、もう少し冗長性やトラブルへの即応力が求められるのかもしれない。
現代人の「ETC依存」?現金派も見直されるべき?
ETC搭載がスタンダードとなった時代だからこそ、逆に設備トラブル時の現金決済レーンへの流入を考える必要があるだろう。あまり使われない現金レーンが意味を持つ瞬間が今回訪れたようにも思える。「もはやETCがなければ走れない」という過度なETC依存は、いざというときの強靭さにおいて、今後の社会の隠れたリスクの一つかもしれない。
国内外での対応例から学ぶこと
海外の場合、混雑時に実施される対応策とは?
海外道路インフラの管理では臨時料金所係員配置、複数の冗長システム導入、さらに混雑時はフリーパス(通行料無料化措置)の議論まで存在する。日本国内でも混雑解消の臨時措置をより柔軟かつ迅速に取る必要があるとの声が交通専門家から上がっている。
考察:「高速道路」再点検のチャンス?今できる我々の対策とは
ドライバーは渋滞時のストレス軽減方法を!
高速道路の渋滞時におすすめしたいのが、podcast視聴やオーディオブック、さらに好きな音楽を気分転換に活用すること。仮に「忍耐力選手権」が実施されてしまった場合を想定して、自分なりの渋滞回避テクニックや、ストレスを緩和させる手法をこの際身につけてしまおう。
行政側の課題と対応
また行政や高速道路会社側には、再発防止のために、広報体制・交通情報提供の改善、代替手段(迂回路案内や公共交通への誘導)、さらに更新作業・点検実施スケジュールの分散化など細かな施策を検討する責任もあるだろう。
まとめ
今回のETCレーン一部閉鎖による騒動は、単なる「忍耐力選手権」と笑える範囲ならよいが、社会の重要なインフラの弱点や課題を浮き彫りにした。混乱を教訓にインフラの堅牢性を高め、利用者自身も明日のために新たな心得を持つことこそ必要だ。次に渋滞にはまったとしても、選手権メダリストにはならずに済むかもしれない。
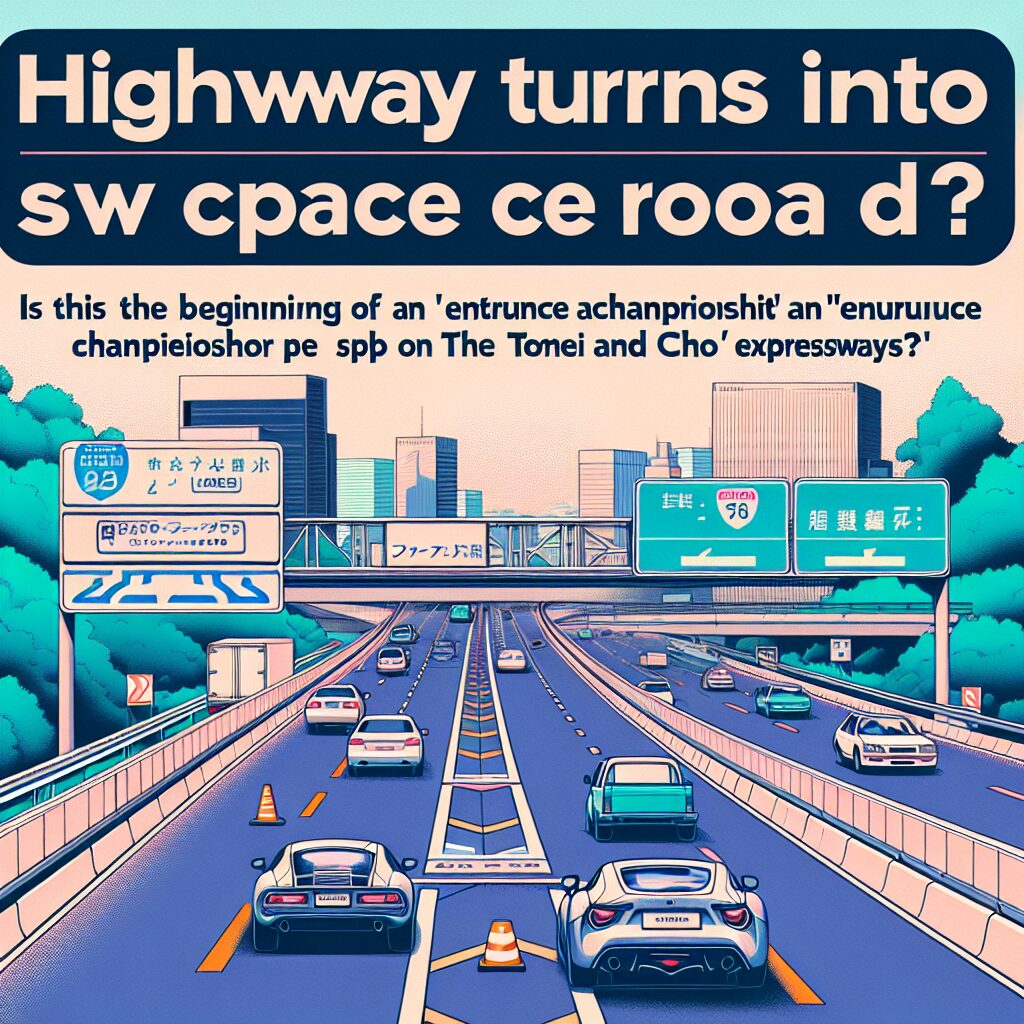







コメント