概要
勢いが止まらない中国EVメーカー。その売上はすでに16兆円規模に達し、グローバル市場を爆走中だ。一方で世界の自動車市場を長らくリードしてきた日本企業は、まるで「充電切れ」に陥っている状態。かつての誇り高きものづくり王国は、このままEV時代に置き去りにされてしまうのか?世界の自動車業界を揺るがす大革命について、わかりやすく深掘りしていこう。
勢い止まらぬ中国EVメーカー、その実力とは?
急成長の理由はそこだった!
中国のEVメーカーの成長スピードには舌を巻くばかりだ。BYD、小鵬汽車(Xpeng)、蔚来汽車(NIO)、理想汽車(Li Auto)など名のある新興プレイヤーは、次々と新車種を発表、売上高はなんと総額16兆円を超えている。
これほどまでに伸びている理由には、中国政府の「EV推進」政策による後押し、そしてスピーディで大胆な技術投資と分かりやすいマーケティング戦略が存在する。また、スマホのような直感的な操作性や安価でも高性能かつスタイリッシュなデザインが若年ユーザーに大人気だ。
EVシフトを牽引する中国市場の開拓力
また中国市場は、世界最大規模のEV市場であるだけでなく、新しい技術やサービスが試される巨大な実験場になっている。「車は電動スマホのようなもの」と、「未来の当たり前」を自然に受け入れる消費者が多く、その勢いを武器に中国企業はグローバル市場へと飛び出している。
さらに、中国はバッテリー産業でも強さを発揮。EVの性能の鍵とも言えるバッテリー技術とそのサプライチェーンを抑えているため、中国企業の競争力はさらに増しそうだ。
ちょっと待って、日本企業は「充電切れ」なの?
トヨタを代表とする日本企業のジレンマ
長年蓄積してきたガソリン車やハイブリッドといった強みが裏目に出て、日本企業はEVシフトへの対応を後回しにしてきた傾向がある。「ハイブリッドこそ本命」という思想が、気づけば足かせになり、新興企業が目を覚ますようなスピードで進化している時代の変化についていくのに遅れをとってしまった。
嫌われるスピード感不足と保守的企業体質
加えて、保守的な判断基準に縛られ、日本企業が新しい投資やチャレンジを避けてしまったことも指摘されている。トレンドに遅れる理由が、EVの性能不足やインフラ環境が未整備だということだった。しかし現状では、性能もインフラも中国をはじめ世界各地で急速に改善され、日本製EVが完全に出揃う前にマーケットは動き出している。
実は明るい?日本企業の再「充電」可能性とは
日本が誇る技術力と信頼性
しかし、ずっとガソリン車やハイブリッド車を作り続けてきた日本企業は、精密な生産技術や品質管理、さらには長寿命なバッテリー開発において深いノウハウを持っている。いわゆる「品質の日本」というブランドイメージはまだまだ健在だ。
足元から再スタート、巻き返しのカギは?
日本企業が復活するためには、思い切った経営判断でEVシフトを急ぐことに加え、官民協力で自前のEVインフラ整備をスピードアップすることだろう。EV専用プラットフォームの確立、中長期的な企業間連携、これまで培った電池技術やリサイクル技術の強化が挙げられる。これら日本ならではの高付加価値を前面に打ち出せば、世界が求める品質と持続可能性を両立できる可能性が大きい。
ここが大事!成功のヒントを海外から
テスラに見るスピード感の重要性
電動化の代表格であるテスラは、少ないラインナップで効率的な生産システムを構築した。また、調達から販売まで徹底した効率化を推進し、ユーザー体験においてもITを融合している。日本企業もこれを見習って、柔軟で効率的なサプライチェーンの構築と、デジタルを活かした顧客体験の改善が求められるだろう。
まとめ
かつて世界が追いかけた日本の自動車産業は、EV時代への転換点において後れを取っていることは事実かもしれない。しかし、日本企業がこれまで築いてきた精密な製造能力、蓄積した電池技術、リサイクルやメンテナンス面での実績は、EV時代の勝者となりえる潜在力を秘めている。「充電切れ寸前」と笑われても、最後に意地を見せれば「大逆転」もあり得るのではないだろうか! 10年後、「あの時の判断が日本企業の復活点だった」と言われる日が来ることを信じて、温かく(そして時に厳しく?)見守っていこう。


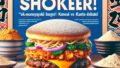





コメント