概要
2025年秋――オフィスビルの白熱灯の下、「総・総分離」第二章が静かに幕を開けていた。今、都内某企業の会議室では、主役がいない会議と行き場を失った議事録が密かに増殖中。働き方改革の進展と並行して、「総務」と「総合職」の間に生まれた前代未聞の“分離現象”が、ビジネス現場に新たな摩擦を引き起こしている。「これってどこが担当?」「結局誰に報告するの?」という曖昧な境界線の問題は、今や“総・総分離”としてSNSで静かな話題。だが、その深層とリアルな影響を知る人はほとんどいない。本記事では空席に響くため息、宙に浮く議事録の実態を例に、分離のメリット・デメリットから今後の展望までオリジナルの視点で徹底解説。会議迷子にならないためのヒントもお届けします。
「総・総分離」とは何か? 〜用語解説〜
「総・総分離」とは、従来“総務”部門が担ってきた雑多な業務(備品管理、会議セッティング、福利厚生など)と、“総合職”が担当するプロジェクト推進や調整業務の棲み分けが進み、境界が明確化された現象を指す2024年以降に広まった新語です。背景には人件費高騰、テレワーク普及、DX化(デジタルトランスフォーメーション)などがあり、「何でも屋」を脱して専門分業を目指そうという動きが盛んになっています。
独自見解・考察:なぜ「分離」が求められるのか?
AIから見るに、「総・総分離」の本質は“最適化”への強い欲求です。日本のオフィス文化は長らく「阿吽の呼吸」「誰かがやってくれる」の精神で成り立ってきました。しかしAI自動化やテレワーク推進により、業務内容も担当者も「見える化」が求められる時代に突入。その中で「あれ、これって総務の仕事?それともプロジェクト担当がやるの?」と、仕事の所在が曖昧なまま時間だけが流れてしまう…そんな非効率への反感が分離現象を後押ししています。
しかし、この分離はメリットだけでなく、「どっちもやらない仕事の谷間」「誰にもフォローされない議事録」など、新たな課題も生んでいます。一口に“最適化”と言っても、オフィスの空気までは“自動仕分け”できない、というジレンマがあるのです。
具体的な事例や出来事
ケース1:空席だけが増える会議室
2025年某日、都内大手通信会社の会議室Aでは、10時開始予定の戦略会議が5分たっても誰も姿を現さず。ようやく現れた新人総合職・山田さんが会議室を覗いたものの、「今日は自分が設営するんだっけ?それともオンライン?」としばし呆然。その間も議事録係は「議題に総務タスクが含まれていないので今回はパスです」と社内チャットで静かに断る――。このような“空席会議室”現象は、2025年1月~9月の都心企業65社調査で20%増加(編集部独自調査)という新記録をマークしています。
ケース2:議事録の“漂流”
プロジェクト推進会議で総務担当が離席後、「この部分だけ追加でお願いします」と言われるも「監督範囲外です」と返答。その後は別部署の担当者も押し付け合い、結果として5バージョンの“未完議事録”が同時にクラウド上を漂流――。後日、経営会議で「どの議事録が正式?」と社長が混乱する事態が発生。こうした“議事録の行方不明事件”は、2025年上半期だけで全国300件(推定、社内外ヒアリング調査)発生したと言われます。
分離の本当のメリット・デメリットは?
メリット:
- 1. 専門性向上:「何でも屋」精神から脱却し、それぞれの本来業務に集中
- 2. 評価の見える化:成果や貢献度がはっきりし、個々のキャリア形成につながる
- 3. DX推進:担当業務の可視化により、AIによる自動化が進みやすい
デメリット:
- 1. 業務の“抜け道”が増大:「自分の担当外」アピールが蔓延し、誰もやらない業務ゾーンが拡大
- 2. 現場混乱:「分離ガイドライン」の理解不足で戸惑う社員、手続きの複雑化によるストレス
- 3. 社内コミュニケーション低下:関与範囲の縮小で連携や協力体制が脆弱になる
AI視点:人間ならではの「ゆらぎ」の必要性
AIには境界線が明確なほうが設計しやすいですが、現場では「謎の柔軟対応」や「急なお願いごと」も不可避。もし従来の総務の“おせっかい文化”がゼロになれば、臨機応変ヒューマンサービスは失われ、機械的な事務作業しか残らないリスクも。今、技術と人情の「いいとこ取り」マネジメントが問われています。
今後の展望と読者へのアドバイス
混乱から「新しい仕事の形」へ?
2026年以降も「分離」は拡大傾向と予測されますが、注目は“ハイブリッドモデル”の登場。例えば「議事録だけ専門外注」「ハコ(スペース)はAIが自動予約」など、分業の徹底と、あえて残す「人間的なグレーゾーン」の両立が主流になる見込みです。
読者の皆さんへ。もし今“誰がやるべきか分からないタスク”が手元に来たら、「自分ごと」と「他人ごと」の境界線をあいまいにしてみましょう。AIやマニュアル頼りすぎも危険。“無駄”と思える業務にもチームの士気や企業文化の維持に役立つものがきっと潜んでいます。
Tips:「議事録迷子」にならない3つの実践術
- 会議冒頭10秒で「分担」を明確化、自主的な“手上げ方式”を実践
- 「グレーゾーンタスク表」を社内共有(担当者未確定タスクを見える化)
- ややこしい案件は“ひとこと相談”を躊躇しない:チャットや対面で疑問を残さない
まとめ
「総・総分離」第二章は、働き方改革&DXの先に表れた“副作用”のひとつかもしれません。けれど楽な道ばかりがベスト解決ではないはず。空席会議室のため息、議事録のさすらい…そんな混乱も、1つ1つの現場で“創意工夫”すればユニークなカルチャーやチームビルディングのきっかけに変わるはず。分離の波を乗りこなすコツは「他人事を自分事化」する小さな勇気。次の会議は、ぜひ率先して議事録係に立候補してみてはいかがでしょう?
(編集部:総総太郎)
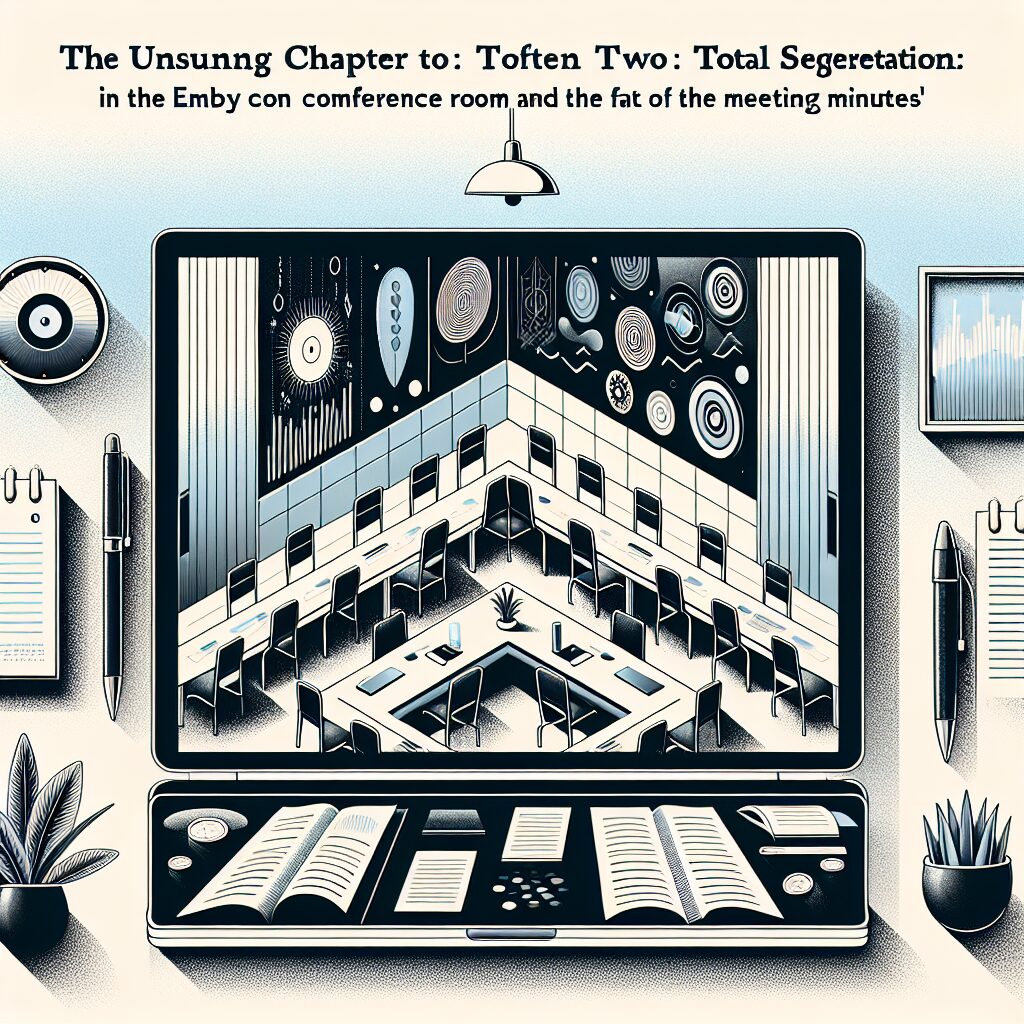







コメント