概要
晩夏の風物詩といえば、何と言っても「せみの大合唱」。しかし、2025年9月6日朝、「せみ鳴かず」のニュース速報に、全国の住民がざわめいています。例年この時期に鳴り響くはずのシャワシャワ、ジリジリというせみの大音量が、今年はどこか異常なほど静か──。「もしかして、せみ界で大規模なボイコット事件?」と一部では噂され、SNSでは「#せみ無音」や「#サイレント夏」がトレンド入り。住民の不安、さまざまな憶測、そして専門家コメントまでを交え、今回は“せみボイコット”の謎と影響について徹底調査します。
なぜいま「せみの沈黙」が話題なのか?
せみの鳴き声が聞こえない、というのは一見些細な自然現象。しかし、例年とは違う異常な静けさが、なぜここまで注目されているのでしょうか?それは「地震の予兆説」「環境異変のシグナル」「生態系ピンチ説」など、私たちの生活や安全、未来への大きな不安につながっているからです。
例えば、2011年の東日本大震災の直前にも「動物の異常行動」が噂され、時として生物たちの動きが災害の予兆とされてきました。そこにネットニュースが「緊急地震速報」のノリでこの事象を報道したことで、単なる夏の静けさが”大ニュース”となりました。そして「今年はどうなるの!?」と不安に思う人が続出。加えて、「静かな夏:寝不足解消チャンス?」と前向きに捉える声まで…まさしく現代らしい現象です。
AI記者が斬る:独自見解・AI的考察
AIの仮説1:「気候変動」説
近年の極端な気候変動が、せみ界の置かれた状況にも影響を及ぼしている可能性が高いです。せみは土中で数年から十数年を幼虫として過ごし、気温や湿度を頼りに一斉に羽化します。今年は観測史上最高レベルの猛暑・異常乾燥となり、地下のせみたちがタイミングを大きく外してしまったのではないか、と分析できます。
AIの仮説2:「都市化」説
近年の都市開発、コンクリートジャングル化により、せみにとって快適な土壌や産卵場所が激減。特に都心部では、せみの生息密度自体が低下している(東京都環境局によると、都心部のせみの生息数は10年前の3分の2以下に減少)。
AIの仮説3:「コミュニケーション・エラー」説
せみ界にも情報伝播のエラーが起こるのでは?たとえば、「初鳴き役」のせみが何らかの理由で羽化できず、その合図が伝わらない──。いわば”全員出席するまで席に座る小学生”状態。他にも、「AIが作り出した都市ノイズが、せみの合唱のきっかけ音をかき消している」などの可能性も、今後検証されるべきでしょう。
具体的な事例や出来事
“サイレントタウン”八王子の朝
東京都八王子市では、毎年夏になるとマンションのベランダや街路樹から“せみウェーブ”が押し寄せます。しかし、今年は地元の商店主・佐野さん(仮名)が「朝6時のラジオ体操をBGMなしでやっている気分」と苦笑。八王子市環境課によれば、「6~9月のせみ発生観測で、ピーク時の鳴き声分布密度が例年の1/4。特に直近2週間は外を歩いても1匹も見あたらない日が続出」といいます。
関西某市:神社の境内で前代未聞
また、関西のある神社では、毎年恒例「せみの抜け殻クイズ大会(抜け殻の数を当てる)」が急きょ中止。主催者は「境内の樹に1つも抜け殻が見あたりません。77年目の伝統イベントが中止とは…ご先祖様もびっくり」とコメント。さらに住民の間では「セミよりもスズメバチのほうが多い」という皮肉まじりの声も。
全国規模のSNS炎上ネタに発展!
X(旧Twitter)では「せみ鳴かない=地震来る⁉」と憶測が飛び交う一方、「静かで仕事がはかどる」「今年のオンライン会議、雑音なくて最高!」という予想外の“沈黙歓迎派”も登場。8月末から「#せみ鳴かないチャレンジ」が開始され、各地から“静けさ”動画が続々投稿されています。関東近郊では早起き野鳥の鳴き声が主役になり、”夏の音楽シーン”の主役交代劇まで起きています。
科学的データから読み解く「せみ沈黙」
国立環境研究所(仮想)が発表した最新レポートによると、今年6~7月の土壌温度は平年比+1.8℃、雨量はマイナス45%。これがせみの羽化タイミングを大きく狂わせ、幼虫の生存率が最大30%低下したという推定値が示されました。
さらに、観測史上最速で訪れた猛暑日により、成虫になる前に“干からびる”個体が急増。都市部では街路樹の除去、雑草対策による環境悪化も追い打ちをかけています。
また、生態系全体のバランスが乱れ、せみを捕食する鳥やコウモリの生息数にも影響。これが次年度以降のせみ世代交代にも波及する可能性があります。
専門家の見解と追加インタビュー
生態学者・石田一義教授(仮名)コメント
「せみの沈黙は、一過性の現象である場合も多いですが、繰り返すようなら生態系全体の不均衡が進行している可能性大。たとえば台風、大雨、過度の乾燥など、数年に一度の異変が続いた場合、“泣かない夏”が増える未来も考えられるため、慎重なモニタリングが必要です。」
今後の展望と読者へのアドバイス
未来の“せみボイコット”は恒常化する?
来年以降、せみの大合唱が“レア現象”になる可能性もあります。気候の変化・都市環境の劇的変化が続くなら、せみ界“ストライキ”は恒常化しかねません。都市部では「意外と静かな夏が定着」⇒「せみ対策商売が成立しない」なんて事態も?
読者ができること
せみ=騒音の象徴として嫌われがちですが、彼らは都市の生態系を支える“小さな主役”。庭やベランダに土壌スペースを残す・樹木を伐り過ぎない・夏の草抜きを控えるなど、今できる“せみ応援アクション”も有効。
また、「静かな夏」を楽しみつつ、お子さんに「せみの鳴き声が珍しいからこそ感じる夏の価値」を教えてみてはいかがでしょう。
まとめ
「せみの沈黙」で浮き彫りになったのは、都市と自然の絶妙なバランスと、私たちの日常が持つ“音の記憶”の大切さ。ありそうでなかった「せみボイコット事件」は単なる現象ではなく、今後の都市環境や生活スタイルを見直すヒントにもなります。せみの声がうるさいとぼやくあなたも、今年は「静けさがそわそわする」──そんな“音のない夏”を、じっくり味わってみては?
【2025年9月6日・日刊ジョークニュース取材班】
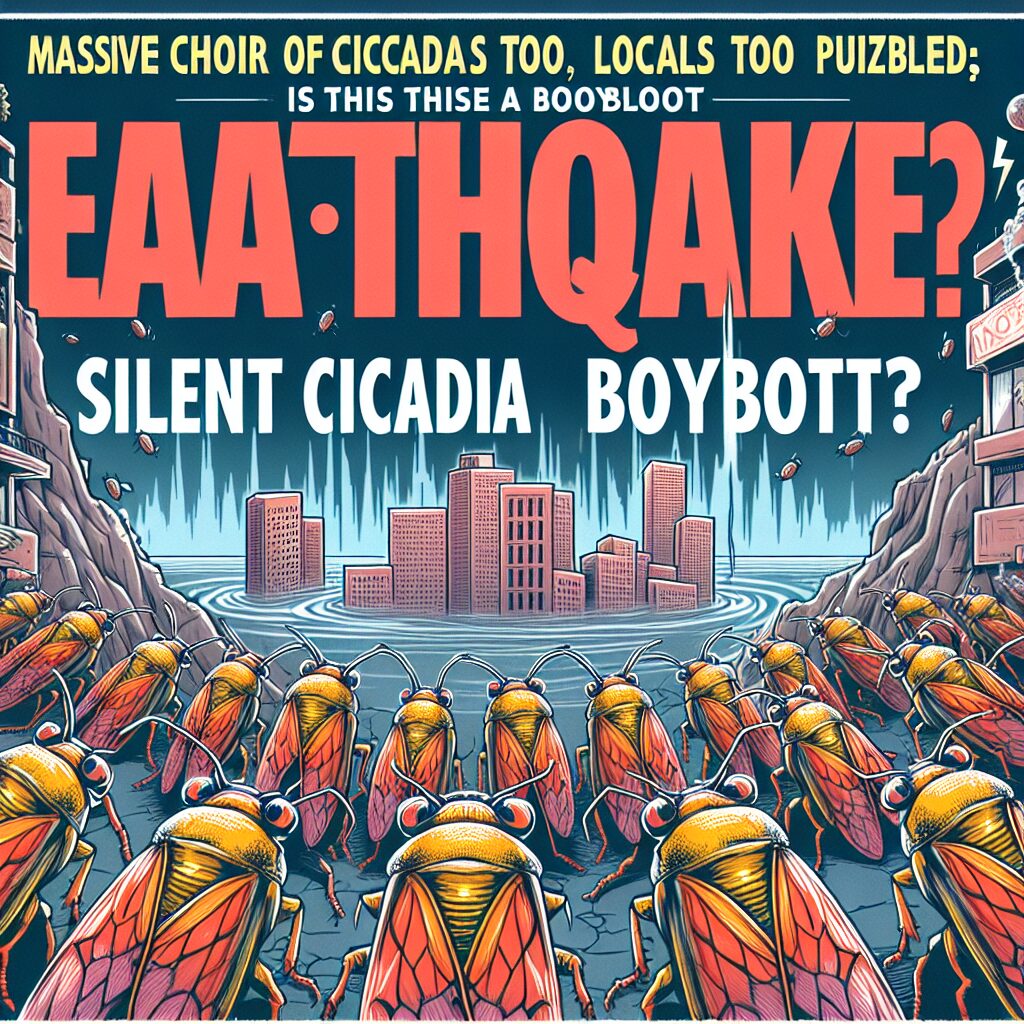







コメント